2009年09月28日
芥川洪水と殉難碑
歴史が偲ばれる景観

↑増水した阿久刀神社付近の芥川(1983年撮影)
目下台風シーズンですが、今年は襲来なく過ぎるのでしょうか。
芥川は昭和10年と28年、42年に決壊しています。昭和10年6月28日から29日にかけての豪雨は未曾有のもので、1時間に100mmを越える大雨であったといわれます。
29日未明の午前2時、阿久刀神社東の堤は、今にも決壊するという寸前に至り、寺の鐘や半鐘が一斉に打ち鳴らされ、カネボウ(現JT)の汽笛が轟々と鳴り響き、想像を絶する緊迫感が住民を襲いました。(清福寺町太田晴己氏著書より)


消防団の対応ではこと足りず、陸軍工兵第4大隊に出動を要請、1個小隊が応援に駆けつけ、「木流し工法」による護岸作業中、もみじの木に上っていた兵は楓の木もろともに濁流にのまれ、行方不明になったのです。
その殉職された上等兵北野小一郎さんの慰霊顕彰碑が真上門前橋を少し南に下がった桜堤に建てられています。
建立者は当時の高槻町長磯村弥右衛門氏、今ではこの慰霊碑に気づかず通り過ぎる人は多いようです。
撮 影 日 2009年9月21日
撮影 場所 清福寺町(地図)
投 稿 者 古藤幸雄
↓ランキングに参加してます☆是非一日ワンクリックお願いします♪m(__)m

Posted by 高槻市
at 07:58
│Comments(7)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。







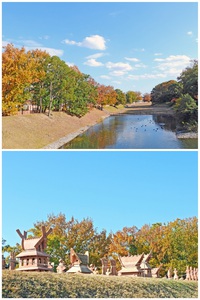













 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン






たまたま昨日、阿久刀神社に行き、ちょうどこの場所を見ていました。
桜堤の東岸に水位のメモリが書かれていて、「あの高さまで水がくるようなことがあるのだろうか」と話したばかりでした。
殉職された上等兵北野小一郎さんのご冥福を祈ります。
毎年、日本の何処かで洪水による犠牲者が出ていますが、ありがたいことに、高槻はもう何十年も台風の直撃やひどい集中豪雨がありません。
ということは、洪水の恐ろしさを実感していない人が大人になり、社会の中枢要員として活躍していることになります。
人間誰しも、体験のないことには鈍感になりがちです。
そのことに年寄りは不安を感じます。
治水事業は100年に一度の大雨を考えてやるべきだと、昔聞いたように思います。
昭和10年からまだ100年経っていません。もっと凄い洪水があるかもしれません。
昭和10年以降にやった治水工事が今老朽化していないか。川底から堤防の天辺までの距離はいくらとしたのか。気になります。
先だっても、このブログで浚渫のことが出ていましたが、いくら立派な堤防でも、川底が上がったら、それこそお手上げです。
ブログに掲載した写真は、通常の増水時の写真で、この程度の増水は、年に1、2度はありますが決壊に至るような水嵩ではありません。
昭和10年の洪水は、北野上等兵が濁流にのまれた直後に上流の大蔵司の上川原が決壊し、その氾濫の結果一気に清福寺あたりの水量は減じたので北野上等兵が人柱になられたとみんな涙し祈ったといいます。
大蔵司の土手際の民家では逃げ遅れ、天井を破って屋根に避難し救助を待った家族もありました。
また、西之川原から大蔵司方面に郵便配達をしていた郵便局員は
濁流に押し流され、大蔵司の我が家の裏の椋の大木にしがみついていたのを救出されたといいます。村中の屋敷や屋敷畑は川原になり、土石が1尺以上も覆いました。
豪雨は大抵台風を伴っており、昭和28年の決壊は13号台風の襲来によるものでした。
ものすごい強風で、屋根瓦はどっと木の葉のように空に舞い上がり、外に出られないので覗き窓から芥川を見ていると、濁流が堤防より高く、炎のように逆巻くのが見えました。同時に濁流は堤防を越えていたのです。
このときも、格納庫や線路上にある土汽車は警笛をけたたましく鳴らし続けていました。恐怖と悲しみの悲鳴のように聞こえました。
風が少し治まったので、中堤に出てみると、木製の大蔵司橋が流失しないように、建設省の作業員(土汽車関係者)が必死で橋にロープをかけ、土手に杭を打ち、それにつなぎ止めようとしていました。橋が流されると、下手にある土汽車の橋に流木がひっかかり、土汽車の橋脚も流されるからです。
この工事はむなしく、濁流は堤防を破壊することなく、外側の田んぼ側でどっと吹き出し、あっと言う間に大蔵司橋もろとも堤防は視界から消えてしまいました。瞬く間に3〜400mの土手が流失し、稲穂の実る田んぼは一面褐色の激流に変わっていました。
先日、芥川倶楽部の幹事会があり、私はオブザーバーで招待されました。そこでの意見、「川原や土手に独り生えの雑木が茂っているのを伐採した輩がある。市や河川管理事務所にだれがやったのか問い合わせたが、どこも依頼や指示したところはない。雑木は野鳥のねぐらや巣になる大切な場所、伐採などもってのほか」
という主張がありました。
せいろうさんがおっしゃる通り、洪水の恐ろしさを実感していない人が大人になり、社会の中枢要員として活躍している時代です。川床の雑木が増水時に流木やごもくをひっかけて流路を妨げ
決壊の要因を作ること、土手の雑木は台風で根っこから引き抜かれて倒され、土手が破壊されそこから決壊が始まることなど少しもご存知ありません。
土木事務所の責任者は、川床の土砂は川の体積の20%を越えるまでは除去しないことになっていると府の方針を述べていましたが、どこからそういう基準ができあがるのか唖然として聞いていました。土木事務所が放置するのなら、自治会が川床の雑木を切り倒しますがと伺うと、即答しかねる雰囲気でした。
被害が出てから反省するいつものパターン、そんな気がしてなりませんでした。
なんて大真面目で言う人がいるんですね。
環境や自然保護は大切なことで、そのためにも治水をしっかりやる必要があると思います。堤防が決壊すれば、洪水によって全てが破壊されます。
素人の考えですが、川底の浚渫は毎年やるほうが、案外安くつくのではと思います。
土砂が川の体積の20%を超えて浚渫すると、工事が大掛かりになり費用も高くなるのではないでしょうか。
考え方として、先ず、浚渫は毎年やることにし、その上で、浚渫費用が少しでも安くできるよう知恵をだして、(例えば、土砂を手近な田畑に入れるとか)継続することが大切だと思います。
「天災は忘れた頃にやって来る」ものですので、「備えあれば患えなし」の高槻にしたいですね。
きのう現地に行って碑文を読みました。きっかけをいただきましてありがとうございます。
この災害事実を周りの人たちに伝えます。鯉のぼりの祭典の現場にこんな歴史事実があるとに少なからず驚きました。
去年新井白石の「畿内治河記」を読み、それが縁となっていささか河村瑞賢の淀川治水事業を調べました。
また今年6月、市内唐崎にある堤防修復記念碑2基の碑文を解読して若い友に深く研究するように慫慂(しょうよう)したところ、その友は明治元年の修復を指導監督した関義臣の治水事業につき地元はもとより鳥取県や福井県にまで調査の手を伸ばして精しく調べあげています。
さて芥川倶楽部や河川管理事務所、また土木事務所の関係者の発言は興味深く読みました。
わたしは治水技術のシロウトですけれども常識は人並みに有していますから、下の碑文に同意しております。
唐崎の「修堤碑」(明治18年災害)に撰文者・土屋鳳洲が東西千古の名言を記しています。
「治水にもと奇策なし。地勢を相(み)、堤防を謹しみ、水勢の趨(おもむ)く所を順にするのみ。」
芥川倶楽部や河川・土木事務所の関係者にこの文章を、特に「水勢の趨(おもむ)く所を順にする」の箇所をじっくり吟味してほしいものです。
いつもながら、含蓄のある名文で敬服いたします。
唐崎の碑の存在は、昔西面にある七中に勤務していましたので知っていましたが、土屋鳳洲という学者はどんな方か知りません。
しかし、撰文は治水の本質に迫る名文ですね。「水勢の趨く所を順にするのみ」ですか。いい言葉です。
今、津之江公園に人工池を高槻市が構築し、在来種の魚類などを飼育、外来種を入れないために、市民の立ち入りを禁じていると聞いていますが、自然に逆らって自然を取り戻そうとする愚行としか言いようのないことをする行政担当者にも是非この土屋鳳洲の言葉を読ませてあげたいものです。
学の無さと目の悪さも手伝って断念してしまいました。
その後こちらの投稿に気づき、皆さんのコメントも含めて読ませていただきました。
勉強になりました。ありがとうございます。