2009年10月14日
龍吐水と太鼓
歴史が偲ばれる景観

「昔の消火用水槽?と太鼓」が掲載されましたが、同様の写真を紹介します。
これは郡家村の庄屋宅の長屋門の軒下に吊るされた龍吐水です。(昭和47年撮影)
私の住む集落にも2軒の旧家の軒下に昭和40年代末まで吊るしてありました。

村の寄り合いや非常時の合図に太鼓が打たれました。これは霊仙寺町の元阿武野村村長宅の天井に吊るされた太鼓です。(H21,4撮影)
今は使われていません。

明治以降になると、龍吐水は車に乗せられて移動しました。重量が結構重いので担いで運ぶのは大変だったからです。
上の写真は名神高架下で保存している昭和40年頃まで使用されていた龍吐水です。

江戸時代は、富農層は自宅に水鉄砲を備えていました。藁屋根に飛び火した火の粉を消す道具です。
撮 影 日 昭和47年他
撮影 場所 郡家村、霊仙寺町
投 稿 者 古藤幸雄
↓ランキングに参加してます☆是非一日ワンクリックお願いします♪m(__)m

Posted by 高槻市
at 09:00
│Comments(5)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。







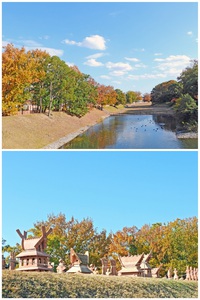













 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン






ポンプ(水鉄砲)の部分も写っていますね。
自宅に水鉄砲があるのは富農層 というのは、びっくりし、なるほどと納得しました。
名神高架下で保存してある龍吐水はぜひ見に行きたいと思います。
車輪つきの龍吐水は大蔵司自治会の所有です。いつでもお越し下さい。
ご案内します。水鉄砲は自宅にありますので、ゆっくりご覧下さい。
それと、個人的なことになりますが、10月27日城山に登ります。
20余名が参加されます。もしよければ、10時に「かじか荘」前に来て下さい。弁当持参です。山城の縄張りを解る範囲で見学し案内します。
昼食後、1時半より清水コミュニテイセンターで「芥川山城と三好長慶の時代」と題して話をする予定です。
10月27日「城山見学会」と講演会に参加させていただけますか。
四日前に一人で登りましたが、「つはものどもが夢の跡」の感慨が生ずるのみ、縄張などほとんど見当がつかず残念に思っていたところです。
宜しくお願いします。
お誘いいただきありがとうございます。
あいにく10月27日は仕事があって参加できず残念です。
11月1日まで、少しばたばたしておりますので、龍吐水と水鉄砲につきましては、あらためて連絡いたします。
城山見学会、ご参加くださる由、嬉しく思います。
私自身あまり城山に詳しくありませんので、「古文書研究会」会員で
塚脇の福岡吉彦さんに同行を願っています。以前にこの会の要請で
城山の講演をしたのですが、そのとき地元なのに生まれて始めて登ったのです。おっしゃるとおり、曲輪跡や土橋などよほど注意深く観察しないと解りにくいです。
今回、西から登り、東の「猪の鼻」集落跡に降りる予定です。
ここは講演でお話する予定ですが,山城が廃城になり、阿波から来ていた兵士、土工たちはほとんど阿波に帰国したのですが、帰国せず土着した人々の集落だったところです。昭和初期までに全部家はなくなりましたが、屋敷跡や井戸などが残っています。また、猪の鼻から城山、塚脇、原に移住して土着した家の話もします。
三好長慶その人には、世間でもてはやされているほど魅力的な人物だったとは、私自身は考えていません。伝承に嘘もあり、史料に基づいて正確な事実をお伝えできればと思っています。
では、小松先生にお会いできるのを楽しみにしています。
kimamaさん、見学会はご参加いただけず残念ですが、郷土史のお話をゆっくりさせ頂きたいと思っています。大蔵司で私の名前を言っていただければ、我が家はすぐにわかります。浄光寺の真南です。
霊山寺もご関心があれば、いつでもご案内します。元村長宅は祖母の実家、寺は友人が住職でかれも博学多識で、中国語が専門で仏典の翻訳も沢山しています。