2008年06月24日
自転車は・・・そうですよね!
街路の景観
自転車は本来軽車両なので、車道を通ることになっています。でも車が増えた数十年前に「自転車は邪魔だ」という自動車運転手からの意見があったのかどうか知りませんが、標識などがあるところでは、歩道を通らなければいけないことに。しかし「歩行者に迷惑のかからないように歩くようなスピードで」これでは自転車の意味がありません。
最近、歩道でもスピードを出して走行する自転車が増えたため歩行者と自転車の事故が増えています。そこで今年に入り警察や国は対策を考え始めたそうですが・・・・。
この写真は、歩道が広く本来自転車も通って良い所(自転車歩行者道の標識がありました)ですが、行く手を阻む棒(車止め)があったり、段差があったり、結局、自転車にとって快適ではありません。ましてや緩やかな上り坂。子供を乗せたお母さんは力を振りしぼりペダルを・・・・・。
やはり自転車は車道の路肩部分(歩道と車が通行する間の部分)を走行するのが快適なようです。
欧米では自転車専用道が網のように整備されているように思われがちですが、基本は車と自転車が共存しているらしいです。つまり車のドライバーは自転車を「仲間」として認識しているようです。
撮 影 日 2007年3月17日
撮影 場所 富田町4丁目(地図)
投 稿 者 高麗敏行
↓ランキングに参加してます☆是非一日ワンクリックお願いします♪m(__)m

Posted by 高槻市
at 08:10
│Comments(8)
この記事へのトラックバック
自転車で暮らす楽しい街と言うテーマで1年6ヵ月前に書いた文章を転載しました。駅前駐輪を眼の敵にするのではなく、みんな自転車で生活しましょうと言う呼びかけです。
「自転車で暮...
「自転車で暮...
自転車で暮らす楽しい街【高槻ライオンズクラブ物語2008続編】at 2008年06月25日 19:43
この記事へのコメント
投稿者:高麗敏行
補足します。写真投稿後、最近になり道路交通法及び同施行令の一部が改正され、施行されました。(6月1日より)
(改正の概要)
自転車が歩道を通行することができる場合
これまで道路標識等により通行することができるとされている歩道を通行することができます。
この場合、道路標識等により通行すべき部分が指定されているときはその指定された部分を、指定されていない場合は、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しながら通行しなければなりません。また、歩行者の通行を妨げることとなるときは、一時停止しなければなりません。
(道路交通法第63条の4)
新たに次のような場合にも歩道を自転車で通行することができるようになります。
○児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合
○70歳以上の者が運転する場合
○安全に車道を通行することに支障を生じる程度の身体の障害を持つ者が運転する場合
○車道等の状況に照らして自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められる場合。
ただし、警察官等が歩行者の安全を確保するために必要があると認めて歩道を通行してはならない旨を指示したときは歩道を通行することはできません。
(道路交通法第63条の4第1項第2号に並びに道路交通法施行令第26号)
車道内で道路標識等により自転車の通行すべき部分が指定されているときの通行方法について一部変更がなされました。
歩道内は徐行しながら通行しなければなりませんが、歩行者がいないときは、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で通行することができます。
(道路交通法第63条の4第2項)
歩道内に自転車の通行すべき部分が指定されている場合、歩行者はこの部分をできるだけ避けて通行するように努めなければなりません。
(道路交通法第10条第3項)
児童(6歳以上13歳未満)や幼児(6歳未満)が運転する場合、その保護者は乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
(道路交通法第63条の10)
2008年06月24日 16:10
投稿者:いわけん
戦後日本の道路行政は、自転車を軽視、無視しているとよく言われますが、「敵視」すらしてきたのではないかと私は思います。大分以前から高槻駅前に設置されている駐輪装置は高槻の密かな「ええとこ」かも知れませんね。警察関係や道路行政関係の方の発言に報道などで接すると、高度成長の昔覚えた(?)「自動車至上主義」から一歩も抜け出せないのがよく伝わってきます。今の年配の方には「自転車は貧乏人の乗物や」という意識が根強いという話を聞いて驚いたこともあります。
大分前に自転車で旧西国街道を通って学校に通った時期があったのですが、交通規則をよく知らず素朴に「自動車はエラいんや」と思っておられる様子の運転手さんから罵声を浴びることもありました。
171号線や枚方亀岡線などで、通学する小学生の数十センチ横をダンプカーが猛スピードで走り抜ける私たちの日常は地獄と紙一重だと思います。
過剰な自家用車利用を減らして、必要な公共自動車と鉄道、自転車、徒歩交通を中心とした、人間の棲むに値する高槻になんとかしていきたいものですが、前途遼遠という感じですね。
2008年06月24日 17:49
投稿者:kimama
えっ!?そうなんですか?「自転車は貧乏人の乗物や」にびっくり。
写真の道は広くて歩道もちゃんとあっていいですよね。
歩道がこれくらいあれば、良識をもって自転車も走れば問題なさそうにも思います。
国道171号線の大畑町交差点から氷室へ向かおうとすると、なんと、電信柱があると、バスとバスはすれ違えません!
北向きの信号が青になると、まずバイクが、次には自転車が、そしてやっと車です。
富田駅北側の徒歩範囲で歩道の途切れない道がありません。
唯一ベビーカーも安全に通れる道があるのですが、そこにはイナイチを渡る横断歩道がありません。
死亡事故もあり、なんだかエライヒトが視察?に来ていた事もあり横断歩道できるのかしらと思っていたら、「横断禁止」の標識が立ちました。
エライヒト、あなたはここに住んでない
富田駅から北へいく、自転車やベビーカーや買い物カート?が安心して通れる道、お願いします!
2008年06月25日 09:54
投稿者:高麗敏行
いわけんさん、Kimamaさん、コメントありがとうございます。昨年、ドイツの自転車道や路面電車などの交通システムを視察に行ったのですが、ドイツではシスターも自転車通勤しており、街中を自転車で走っている人はみなかっこよく見えました。「環境のことも考えたカッコイイ乗り物」という意識を持っているのではないでしょうか。
Kimamaさんのコメントにある邪魔な電柱のことですが、無電柱化の割合が、諸外国は約30年前のデータで72%(ニューヨーク)~100%(ロンドン、パリなど)です。それに比べ2007年現在の東京、大阪は7%~3%の整備率と、30年の差があっても大人と子供ほどの違いです。
ドイツの地方都市(人口20万人~30万人)の中心部では、車乗り入れを規制したり、一方通行にして、歩行者や自転車走行の空間を確保しています。日本では、ある地区を一方通行規制しようとすると、警察などから「100%の住民の合意がないとダメ!」という話を耳にします。「横断禁止」ではなく、歩道を連続整備し車を一方通行にする、あるいは地域の方達で道路をどのように使うか、何を優先するか話し合って決めてはいかがでしょうか。
宣伝になりますが、7月12日(土)交流センター5階視聴覚室でドイツ視察の報告会及び高槻の交通まちづくりのフォーラムを行います。(主催:たかつき環境市民会議)時間は14時~17時です。興味のある方は是非!
2008年06月25日 13:20
投稿者:いわけん
高麗さん、情報提供ありがとうございます!高麗さんと一緒にドイツ視察に行ったと思われる研究者氏から、高槻にLRTを実現しようとする運動があると聞きました。高槻の交通がどう変わっていくかは興味あるところなので、参加します。
一般市民の方だけでなく、市議会・市役所・警察の要職にある方にもお越し頂きたいですね!
2008年06月25日 15:15
投稿者:高麗敏行
いずれHPにアップしたいと思っていますが、ドイツでは赤ちゃんの時はベビーカーとして使用し、幼児になったらお母さんの自転車の後ろに取り付けて牽引できる箱(?)を何回も見ました。キッズ・バイクトレーラー(HP参照)と呼ばれているみたいです。(日本のように前後にカゴをつけることはないですね)また、整備された自転車専用道などなど、おもしろい写真を7月12日のフォーラムではお見せしたいと思っています。
よろしくお願いします。
2008年06月25日 18:04
投稿者:せいろう
自転車は優秀な移動機具であり、健康器具だと思いますので、頻繁に使いたいものです。しかし、道路事情や駐輪場などで、快活に使えないのが現状ですね。
日本は人口密度が高い、起伏が多いなどの事情がありますが、自転車活用先進国のヨーロッパから学べることもあると思います。
ドイツ視察報告会、是非聴きに行きたいと思います。
2008年06月30日 04:35
投稿者:いわけん
交通と景観が交わるのは「自動車」の問題です。自動車最優先の政策が交通事故が日常茶飯事の高槻をつくり、我々の自動車依存的な生活態度が郊外に拡散した「溶けた町・高槻」をつくりました。ええとこブログ・景観ワークショップに参加した人や上記のドイツ視察旅行に行った人たちなどが集まって今年「たかつき交通まちづくり研究会」という集まりをつくりました。その主催する「たかつき環境・交通シンポジウム」が11月22日14時から市民会館305室でありますので、ご案内します。詳細はリンク先よりご覧下さい。
2009年10月28日 21:33
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。







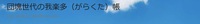














 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン





