2007年04月23日
花の井
歴史が偲ばれる景観
この「花の井」は、平安時代中期の歌人能因法師が使ったといわれる井戸です。
周辺は民家に囲まれているので、所在が非常にわかりにくくなっていますが、周辺の人たちが何代にもわたって守ってきました。
さらに、近年になって、民家が立ち並んだあとも、地域の人たちの手によって、綺麗に維持されており、最近、ジャリなども引きつめています。
また、近くには、能因法師に関連した史跡である、「不老水」、「文塚」、「花の井」があります。
古曽部は平安の世に想いを馳せることのでき、歴史や農地と自然が調和する魅力的な場所で、詩人の小野十三郎が、生前、「大原三千院や落柿舎あたりには負けぬ、古曽部は日本史の中で堂々たる隠棲の佳境でもある」ともいっています。(昭和30年代の古曽部について語ったと思われます)
撮 影 日 平成19年2月20日
撮影場所 古曽部町3丁目(地図)
投 稿 者 神畑善吉
↓ランキングに参加してます☆今何位か見て下さいね♪

Posted by 高槻市
at 08:33
│Comments(6)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。







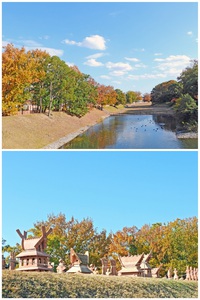













 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン






いまでも、つつじとか四季折々の花が周りで咲くように、近所の人で手入れをされているようです。
ちゃんと「花の井」にしていくのも、すごい大変です。
手入れをされるのは大変でしょうが・・・
残されているのは、とても素晴らしい事で嬉しいですね。
この周辺には花乃井という地名はありません。
なぜ、花乃井中学という名前がついたかというと・・・
http://www.oclions.org/shiseki/7.html
地名の由来を発見すると、なんとなく得した気分になりませんか?
ところで、私は実際、見に行ったことはないのですが、この祠の中にはお地蔵様とかが祀られているのでしょうか?
富田の造り酒屋に、地ビールの見学に行った時にも
「幾つか有った井戸も涸れて、今はこの井戸だけです」と
話されていました。
高槻の数少ない有名人・藤井竹外の漢詩「花井」によれば、幕末の頃は花(桜?)も咲かず荒れていたようです。
水はあったようですが、雨がたまっただけなのかも知れません。
花井井荒花不開 花井の井は荒れて花開かず
残碑字滅半莓苔 残る碑の字は滅し半ば莓苔す
一泓緑浄無人管 一泓の緑浄(=深い井戸の水)は人の管する無く
付與青蛙喚雨来 青蛙の雨を喚び来るに付与するのみ