2007年01月28日
とんどの火祭り
歴史が偲ばれる景観


日本の各地に伝わる小正月の行事で「とんど」と呼ばれる火祭りです。
竹を組み合わせ、正月のしめ飾り等を一緒にしてやぐらにして火を放ちます。その年の豊作や無病息災などを祈る行事です。
最近は少なってしまいましたが、昔のムラでは、あっちこっちで煙や、竹の爆裂する音が聞こえてたことが思い出されます。
撮影場所 東天川3丁目(地図)
撮 影 日 2006.1
投稿者名 原春ニ
↓ランキングに参加してます☆是非一日ワンクリックお願いします♪m(__)m

Posted by 高槻市
at 00:24
│Comments(7)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。







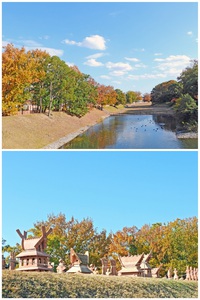













 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン






とんどは、子どもの頃、自然と参加していましたが、最近めっきり見かけなくなったような気がします。
このような、行事は大事にしていきたいですね。
昔は、農家が各自で“とんど”を作り、自分の田んぼで焼いたといわれているそうです。
でも、いま高槻では、広い田んぼもないし、煙とかで近所迷惑とか言われるので、この写真の「とんど」も淀川河川敷でやっておられるようです。
来年こそは見に行こうを思います。
冬休みの宿題で書いてきた書初めを燃やして、煙が高く上がると字が上達すると学校で言われてました。
一般的には「左義長」と言われますが、地方によって呼び名が違うようです。字の上達以外にも、その火で焼いた餅を食べるとその年の病を除くとも言われています。
お正月に門松などで出迎えた歳神を、それらを焼くことによって炎と共に見送る意味があるそうです。
小学生の頃は、大きな焚き火をしているような気分で、竹が焼けて割れる音で歓声を上げたり、火に思いっきり近づいたりして、みんなでおおはしゃぎしました。
呼び名が変わっても、規模の大小はあっても、地域で親しまれる行事として続けてもらいたいものです。