2007年08月02日
城下の町家
歴史が偲ばれる景観

白壁にむしこ窓、格子、素朴なグレーの瓦のむくりの屋根、高槻でよく見かける町家です。
ひっそりと建っていますが、素朴でシンプルでいいなと思います。
昔ここが城下町だったことを思うと、古い家といっても一口に「町家」とくくられるものではなくて、商家や武家や職人さんの家など、きっといろんなタイプのお宅があったのでしょう。
城下町を想像しながら散歩してみようかなと思っています。
撮 影 日 2006年7月
撮影場所 大手町(地図)
投 稿 者 かね子
↓ランキングに参加してます☆今何位か見て下さいね♪

Posted by 高槻市
at 08:49
│Comments(7)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。







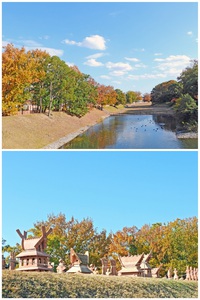













 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン






昔の家のつくりはどの部屋にも風が行き通るよう作られていて、風鈴が涼やかに響き渡る、そんなイメージを持つのは私だけでしょうか?
ちょっと違った視点でこういった風景を見るのも楽しいでしょうね!
町家をよく見てみると、京都によく見られる、間口が狭くて奥行きが深い家の造りが多いことが発見できます。
これは、江戸時代頃に町費が間口に応じて決められたためで、これが実質的に税金の意味合いを持っていたらしいです。
<むしこ窓>
虫かごの形状の窓。
<格子(こうし)>
京町家に特徴的な格子。接道部に用いられる。光を採り入れ、中からは外が見えるが外からは中が見えにくい。ガラスの登場により衰退しつつある。
<裏庭>
町家の多くには裏庭があって、いずれも採光、風の通り道としての機能を兼ね備えている。
<犬矢来(いぬやらい)>
道路に面した外壁に置かれるアーチ状の垣根。馬のはねる泥、犬や猫の放尿から壁を守るもの。泥棒が家に入りにくい効果もある。
2007年8月2日の「城下の町家」のところのコメントにあるのですが、「うなぎの寝床」状の町家が間口に対して税金をかけたためにできたとする説についてです。たしかにweb上にはたいへんたくさんこの説が出まわっています。
税金逃れ説はあきらかにまちがいなのですが、どこからそのような説をお聞きになったのか、あるいはお読みになったのかがわたしの興味のあるところです。古くからいわれているようですが、文献ではまだ発見できません。
ちなみに7月28日にWIKIPEDIAの「京町家」の解説を以下のように修正しました。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E7%94%BA%E5%AE%B6
「町家の立地する敷地は、間口が狭く奥行きが深いため、「うなぎの寝床」と呼ばれる。これは、江戸時代頃に町費が間口に応じて決められたためである【とする俗説が流布しているが、これは誤りである。通りに多くの家屋を建ち並ばせるためには、必然的に間口が狭く、奥行きが深くなる】。」 (【】内を追加しました。)
あまりにもweb上にこの説が多いので、ひとつひとつめーるをだしています。失礼があればおゆるしください。純粋に学術的な興味からコメントしました。
神戸松蔭女子学院大学 中林浩(都市計画学専攻)
baya@js6.so-net.ne.jp
全国の町家を研究されている京都の大学の先生のご講演でお聞きしたことですが、町家には大きく分けて
1.「京町家」と地方の人が京都風を真似た「京都型町家」
2.地方の街道沿いの農家等が宿・商家等になった「在地型町家」
があるそうです。1は上記写真のような「平入り」ですが、2は「妻入り」が多いそうです。
中には京町家とは全く違う形式の「妻入り」農家なのに、「都会風」に見せようとして表だけ「平入り」になっている家もあるそうです。高槻城下と芥川宿の町家がどうなっているか見てみると面白いかも知れません。
以上のようなことはもしかするとご年配の方には常識に類することなのかもしれませんが、若者にとってはかなり注意して見ないと気づかないことだと思うので、受け売りですが、ご参考まで。
「京町家」のコメントについては、WIKIPEDIAを参考に記述しました。
誤りのようですので、訂正させてください。
「通りに多くの家屋を建ち並ばせるためには、必然的に間口が狭く、奥行きが深くなる」と、いうことですね。
今も昔も建て方は、似ていますね。
これからもええとこブログをよろしくお願いします。
また、コメントおまちしています。
コメントありがとうございます。町家の発生については高橋康夫説と野口徹説とかありまして、かなりおもしろいものがあります。しかし、間口税の説は採っていません。
ところが、小中高大でそう聞いたという方が続出していて民間伝承の研究としての興味があります。
なにかわかりましたらまた連絡ください。