2007年03月29日
富田残像
歴史が偲ばれる景観


古くから残る造り酒屋、独特の風情・・・
おや?
近付いて見ると、鉄板(+腰は波板)貼り!
昔ながらの左官による壁ではない。
形態と色彩。
そこに気を使われていれば、記憶の中の残像が呼び覚まされて、私たちは、なつかしささえ感じてしまう。
古き佳きものの継承と現実的事情。
葛藤が予想される中での、これは、ひとつのうまい事例かもしれない。
撮 影 日 07.3.17.
撮影場所 富田町6丁目(地図)
投 稿 者 岩崎卓宏
↓ランキングに参加してます☆是非一日ワンクリックお願いします♪m(__)m

Posted by 高槻市
at 02:29
│Comments(6)
この記事へのトラックバック
激ウマラーメン店「彩色ラーメン きんせい」に再訪しました。
僕らが行ったときは1組が待っていて10分くらいで店内に入れたがその後は平日なのにあっという間に行列完成 人気の...
僕らが行ったときは1組が待っていて10分くらいで店内に入れたがその後は平日なのにあっという間に行列完成 人気の...
色彩ラーメン きんせい(再訪) / 高槻市栄町【abouttimes日記】at 2007年04月02日 17:00
この記事へのコメント
投稿者:こうらい
古くからのモノを残していくことは大変だと思います。また、ライフスタイルや時代、流行など、新しいスタイルが求められることも事実です。
ただ、その街には、独特の色があり、ニオイがあり、あるいは音があります。
何でもかんでも新しくするのではなく、それら街の特徴を活かす工夫が大事ではないでしょうか。
建物の要素である「形」「色」「材質」など全てを新しくするのではなく、この酒蔵のように「材質」は風雨等からの耐久性を考慮し新しいモノ、でも「形」や「色」は酒蔵やその周囲の本来のイメージを壊さないように「同調」させる、そのような工夫が大事だと思います。
今回は、上手くだまされました。あっぱれ!!
2007年03月29日 12:45
投稿者:上ひら
古いものを残していくことは大変だと思います。この杉板を焼いた壁面の材料も、今ではこのような使い方をしないので、特注になるでしょうし、値段も高いんだろうと思います。(だから、見えないところはトタンになった?)
また、この写真には載っていませんが、この酒造の母屋の建物は明治30年代の建築だそうです。(110歳くらい??)
<参考:母屋の写真>
http://www.city.takatsuki.osaka.jp/new/syoko/html/travel0018.html#5
2007年03月29日 13:09
投稿者:松本邦彦
確かにまんまと騙されちゃいますね!
「当然そーやろ」って頭でイメージしてしまうと、目の前にある物をきちんと目で確認するのを、さぼってしまうんでしょうかねえ。
2007年03月30日 02:30
投稿者:おがわ
具体的な事例をなかなか思いつかないのですが、素材はばらばらでも、色なんかを似たようにすることで、連続性というか、統一感は出せますよね。たとえば、植えられている木はいろいろな種類でも、緑が続いてるっていうことで並木になったりとか。
個々の選択の範囲を広げつつ、統一感を図るということのすばらしい事例ですね。
2007年03月31日 01:13
投稿者:miles
今は入手困難な材料や技術を苦労して集めてくるというよりは、むしろ現代の材料や技術を使って建物を継承していくことの方が自然な感じがします。大切なのは、建物の記憶として何を引き継いでいけばいいのかということでしょうね。
2007年04月02日 12:45
投稿者:あわむら
この写真では、壁面の杉板焼の代わりに、トタンを貼っていて上手く工夫してるな!と思います。遠くからだとわかりませんよね。また、こういった時代の流れにそった事例としては、茅葺屋根の上にトタンを葺いている民家があります。
屋根の場合はトタン葺よりも茅葺の方が断然綺麗だと思います。飛騨白川郷の合掌造りは私もとても好きです。
http://www.vill.shirakawa.gifu.jp/
でも、茅葺がどんどんトタン屋根に替わってしまう背景には、手入れや葺き替えにコストが掛かること、茅葺を長持ちさせるために囲炉裏をつかって屋根裏に煙をまぶす生活スタイルでなくなってしまったこと、さらには、茅葺は村の共同作業ではないと維持できず、周りの民家がトタン屋根にしていくと、村全体が茅葺を維持できなくなるとのこと。
人の生活と景観は密接な関係にあるのだと改めて気付かせていただきました。
2007年04月13日 12:06
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。







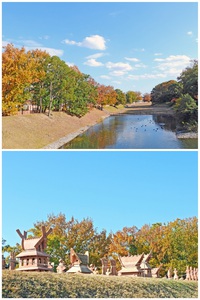













 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン





