2009年10月16日
富田の老舗料亭きんなべ
歴史が偲ばれる景観

現在きんなべがあるあたり一角は、江戸時代前期まで長福寺というお寺があったと言い伝えられているそうです。
その跡地に江戸時代中期ごろ建築されて、約250年間、何度か改築を繰り返し、現在のたたずまいになったそうです。
前の道路からお店を見上げると、手前の方の屋根が短くなっているのがわかります。
何でも、現在のJRができた時に、お店の前の道の拡幅工事をされたのですが、その時に、建物を一部取り壊して道路に提供した名残なのだそうです。


外からも、建物の中に入っても、建築当時から残っているものはほとんど見えないのですが、基礎や柱、屋根裏などは昔のまま残っていて、古い柱の上に化粧板などを張ってあるので、新しく見えるのだそうです。
戦時中は、疎開してきた人を受け入れていたこともあり、部屋の中で煮炊きをしていたので、煤けて黒くなってしまったのを洗いにかけ、手を入れてきれいにされたそうです。

建物が古く、普通の大工さんではできないような仕事は、宮大工さんに依頼して改築し、48年前に料亭を始められたそうです。


富田は酒造りに適した地下水に恵まれていますが、きんなべさんにも、今も3つの井戸があり、実際に使われています。
このあたりは、地盤が堅いので、井戸は、掘りっぱなしになっていますし、石の上に柱が立っているだけでびくともしないのだそうです。
撮 影 日 2009年10月5日
撮影 場所 富田町5丁目(地図)
投 稿 者 kishie
↓ランキングに参加してます☆是非一日ワンクリックお願いします♪m(__)m

Posted by 高槻市
at 07:41
│Comments(3)
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。







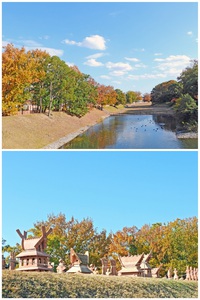













 大阪ブログポータル オオサカジン
大阪ブログポータル オオサカジン






このきんなべさんの写真を見ていると、綺麗~って思うだけなのですが、疎開の人を受け入れて室内で煮炊きをしていたお話をお聞きすると、また見方も変わってきます。
よく日本家屋は、柱や梁の構造材以外は、入れ替えて新陳代謝するのが、世界に誇る特徴だ!といっているのをなにかで読んだことがありますが、この「きんなべ」さんも、こまめに手を入れて、昔の建物を守ってラシャるのですね。
きんなべさんのエピソードまた教えてください。ご紹介ありがとうございました。
少しずつ想い出してきました。
きんなべさんが疎開してきた人を受け入れていた話、いい話ですね。
私の生まれた家でも、一度洗い大工を頼んだことがありました。キレイになっていく様を覚えています。
昔の住宅は一寸した移動もできました。それをする人を転ばし大工と呼んでいました。
屋敷内に3つも井戸があり、全て現役とは、やはり、きんなべさんはスゴイですね。
またいい話、お願いします。
当日いっしょに「きんなべ」さんにおじゃましたのですが、古い建物を美しく使っていくことの手間ひまについていろいろ考えさせられました。
きんなべのご主人が「この柱にこどものころ傷をつけたのも上に張った板に隠れています」と話され、そのあいまにも小さなお孫さんがたたたっと廊下を走ったりして、建物の現役ぶりを実感しました。(営業時間中ではありませんので)